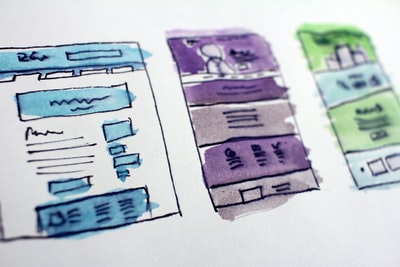心理学の有名な法則の1つに「ジャムの法則」があります。選択肢の種類に関する法則で、判断力を持ちたい!という方にも知っておいてほしい心理学です。
【悩み】
- 心理学の「ジャムの法則」とはなにか説明してほしい。
- ジャムの法則を販売やマーケティングに活かすにはどうしたらいいかな…。
この記事では、「ジャムの法則」とはなにか説明していきます。上記のような悩みを解決できるように書きました。
判断力を向上させたい人が気をつけるべきことがわかります。
ジャムの法則とは

心理学におけるジャムの法則とは、コロンビア大のシーナ・アイエンガー教授によって提唱された法則で、選択肢が多すぎると、選ぶことに困難を感じてしまう心理作用のことです。
例えば、あなたが昼ごはんを食べるときを想像してみてください。お店のメニューに20〜30種類の料理が書かれていると、「どれがおいしいのか…。。」と選ぶのに疲れてしまいますよね。逆にメニューが5種類でしたら、食べたいものも選びやすいです。
つまり、ジャムの法則はあなたが選択するときに、選択肢を増やしても、かえって選びづらくなる可能性があるという法則です。
ジャムの法則の実験

ジャムの法則に関して、選択に関する研究をしているコロンビア大学で次のような実験が行われました。
実験内容
スーパーマーケットでジャムの試食販売を実施しました。
- 6種類のジャムを用意
- 24種類のジャムを用意
どちらの方がより売れるのかを検証しました。
この実験では、種類の多さが売上に関わるのかを調べました。
結果
24種類のジャムを用意した方が、人は多く集まりました。
6種類の試食では、試食した人の30%が購入したのに対し、24種類の試食では、試食した人の3%が購入しました。
つまり、試食のジャムを6種類に絞った結果、購入率は10倍変わりました。
実験結果(まとめ)
試食した人の購入率は、
- 6種類のジャム…30%
- 24種類のジャム…3%
購入率に10倍の差がある!
考察
ジャムの法則の実験結果から言えることは、ヒトは、選択肢が多すぎると考えることにストレスを感じ、選択をやめやすくなるということ。
24種のジャムの中から良いものを選べと言われても…と頭を抱えてしまいますよね。
そして、考えることに疲れたから買うのをやめようとするわけです。
このように、選択肢が多すぎる場合「選択をやめる」人が多いことがわかります。
ジャムの法則の注意点

ジャムの法則の実験結果から、とにかく選択肢を絞ろうとすると失敗する可能性もあります。
ジャムの法則の実験では、6種類のジャムを用意した方が購入率は高い結果になりました。しかし、売上は24種類のジャムを用意した方が高くなる可能性もあるからです。
購入率 6種類>24種類
しかし、売上は、6種類<24種類かもしれません。
24種類のジャムを用意したほうが人が多く集まったので、売上は高い可能性があります。
例えば、24種類のジャムを出したときに、試食に1000人集まっていたとすれば30人が買ってくれたことになります。
しかし、6種類のジャムを出したときに、試食が10人だけだとしたら買ってくれたのは3人です。
このように、売上だけをみれば24種類の方が高い可能性は充分にあります。
ですが、ジャムの法則の実験結果では、購入率に10倍の差がありました。多すぎる選択肢は、判断を鈍らせる効果は実証されていますよね。
最適な選択肢の数は7±2

ジャムの法則の実験を行った、コロンビア大学ビジネススクール シーナ・アイエンガーによると人が選択するときの選択肢の数は7±2がベストだと言っています。
なので、あなたが「選択」する際には、あらかじめ選択肢を5〜9個に絞っておくことで決断力を高めることができます。
また「人に選択してもらう時」にも選択肢は5〜9個に絞って提案した方が相手は選びやすいでしょう。
販売•マーケティングは、目的に合わせて行う

ジャムの法則から選択肢は5〜9種類が適切でした。販売•マーケティングでも、顧客が選びやすいように選択肢を絞ることが鍵となりそうです。
例えば、スーパーマーケットの売り場では、1つのゴンドラ什器にある商品は、7.8種類でしょう。多くても10種類程度ではないでしょうか?
また商品の企画する際も、商品の種類を闇雲に増やすのではなく、本当に打ち出したい商品を絞って企画することが重要です。
このように、顧客の目的に沿って、選択しやすい環境を作ることで売上や顧客の満足度につながるのではないでしょうか。
ジャムの法則(まとめ)

ジャムの法則は、選択肢と人の決断に関する心理学の法則でした。
お店の経営や販売、マーケティング企画などさまざまな事に活かせます。この記事が参考になれば幸いです。